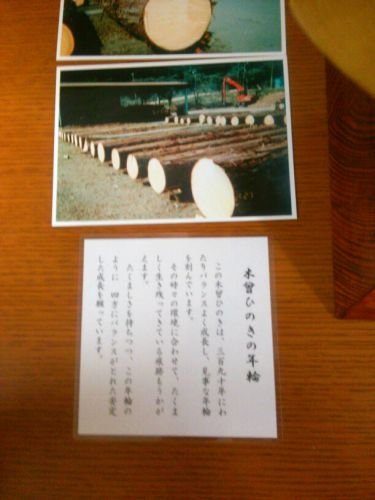ブログ
みなさん こんにちは!!8月の後半は、怒涛のように
研修で、飛び回るスケジュール
でした。
今週の月曜には平塚の社会福祉法人
さんにて、「人間力向上研修」の最終回
が開催されました。
いつも最終回はグランドフィナーレとして
みなさんとこの研修を振り返り、感動を
再び思い返して頂く時間として、とても
大切にしています。
そして今回は、最後に受講生の皆様と記念写真
をとり、その後には打ち上げパーティーへと・・・
サプライズの連続で、この施設ならではの
「暖かさと」を感じ、こちらが感動させて
いただきました。
本当にありがとうございました。
みなさん、こんにちは!!
先週末の22日は鹿児島県で人間力向上研修
を行いました。
この度の企画は鹿児島県のグループホーム
協議会にて開催いただいたもので
鹿児島県のグループホームで働く、中堅職員
の方々約60名にお集まりいただき、中堅職員
向けの人間力向上研修を朝から5時間で、一気に
お伝えさせていただきました。
通常は10時間以上でお話する内容を
グット凝縮する格好で5時間に集約しお伝え
したので、かなり中身の濃いものになった
ものと思います。受講生の方々は少々、お疲れ
だったかもしれませんが・・・・
でも、終了後のアンケートを拝見すると
「あっという間の時間でした」「もっと聞きたく
なる研修でした」など、講師としても概ね
「伝わった感」を持つことができ、ほっとしている
とともに、受講生の方々に感謝です。
さらに、今回の企画をしていただいた、グループ
ホーム協議会の役員の方々には、改めまして
御礼を申し上げたいと思います。
本当に みなさん ありがとうございました。
みなさん、こんにちは!!
今月の20日は東京中野区主催の
中堅介護職の方々に向けた研修
で、人間力向上研修中級編を
行いました。
当日は 中野区の施設や事業所に
働く、主任さん、サービス
提供責任者さん、他のリーダーさんら
中堅職員の方々が
約80名お集まりいただきました。
2時間という限られた時間で
どこまでお伝えできるのか、
不安を感じながらのスタートでしたが
終了後の皆さんのお顔を拝見しますと
お伝えしたいことは、伝わったかな
と感じています。自己満足かもしれ
ませんが(笑)。
次回は、施設長、管理者の方々にお集まり
頂く、「人間力向上研修(上級者編)」
を9月下旬に、また中野区役所にて
開催いたします。
さて、管理者の方々に2時間で何を
お伝えするか・・・・
今 考え中です。
それでは。 みなさん、こんにちは!
今日は、「社会福祉法等の一部を改正する法律案」の
ポイントについて解説いたします。
2014年7月4日に発表された報告書「社会福祉法人制度の
在り方について」、2015年2月12日にまとめられた
「社会保障審議会福祉部会報告書~社会福祉法人制度改革
について~」を経て、第189回国会に提出された
「社会福祉法等の一部を改正する法律案
(以降、「改正社会福祉法」と呼ぶ)」。
安全保障関連等の重要法案審議に時間を費やし、本案について
いつ国会で審議されるのか、状況を注視していましたが、
ようやく先月30日に「衆議院通過」となりました。
残るは参議院審議ですが、こちらは問題なく通過する
ことはほぼ自明だと考えても差し支えなく、
本改正案が法制化されることは時間の問題だと言えそうです。
これからの社会福祉法人に一体何が起こるのか?今回は
特に経営面で大きな影響を与えるであろう本法案のポイント等
について確認してまいります
(社会福祉法人以外の法人の皆様も、地域社会に影響を与えるであろう要素として、是非、ご認識下さい)。
本改正案には大きく2つのテーマ「社会福祉法人制度の改革」と
「福祉人材の確保の促進」が盛り込まれています。
介護事業者の皆様には前項の1つ目「社会福祉法人制度の改革」
の中身について、特に以下の5つのポイントをおさえて
おいていただければと思います。
【その1:経営組織のガバナンスの強化】
議決機関としての評議員会を必置(小規模法人について評議員定数の経過措置)、一定規模以上の法人への会計監査人の導入等
従来より推奨されていたものの、全ての社会福祉法人に
とっての「義務」ではなかった評議員会が「必置」
となったのは、今回の法案の中での最大のポイントだ
とも言えるでしょう。同時に、今回は、評議員と役員、
又は当該社会福祉法人の職員の兼務も禁止となっています。
これは、実態として、評議員を置いている法人においても、
法人理事が評議員を兼務する事が多く、
「理事会の決議=評議員会の決議」となっている
(=本来、評議員会が有すべき(理事会に対する)牽制機能が機能していない)、という問題、
即ち、「ガバナンスの欠如」「透明性の担保」に対する
指摘が背景にあります。また、「一定規模以上の法人への
会計監査人の導入」についても同様の課題認識に端を発しており、
「資金使途にも牽制機能や透明性担保を強化しよう」
という表れだと理解出来るでしょう。
ちなみに、「一定以上の法人」の「一定」の基準については、
当初は「10億」とされていましたが、現時点ではまだ未定の
ようです(もっと引き下げられる可能性もあるとは聞いています)。
【その2:事業運営の透明性の向上】
財務諸表・現況報告書・役員報酬基準等の公表に係る規定の
整備 等
こちらも上記【その1】と同様、「牽制機能強化」「透明性担保」という意味合いが大きいと思われます。
【その3:財務規律の強化】
・役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与の禁止 等
・「社会福祉充実残額(再投下財産額)」の明確化
・「社会福祉充実残額」を保有する法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画の作成を義務付け 等
「社会福祉充実残額(再投下財産額)」とは、世間で指摘されて
いる、いわゆる「内部留保」を指しています。
定義としては、「純資産の額から事業の継続に必要な財産額(=?事業に活用する土地、建物等 ?建物の建替、修繕に要する資金 ?必要な運転資金 ?基本金及び国庫補助等特別積立金)を」
控除等した額」となります。
今後、全ての社会福祉法人はこちらの計算を進め、
自社に「社会福祉充実残額」がどれぐらい残っているのか、
そして、それらをどのように有効に使って行くのかについて、
明らかにしなければなりません。法人の現状によって
バラつきも大きいと思いますが、今までそこまで強く
求められてこなかった新たな業務が現状に付加される事は間違いなく、法人本部としては、相応の心構えが必要となるでしょう。
【その4:地域における公益的な取組を実施する責務】
社会福祉事業及び公益事業を行うに当たって、無料又は低額な料金で福祉サービスを提供することを責務として規定
社会福祉法人として、法人格に相応しい事業をやりなさい(≒営利法人と同じ土俵の事業ばかりでなく、税制優遇を受けるに相応しい事業をやりなさい)という意味だと捉えて差し支えないでしょう。
【その5:行政の関与等のあり方】
所轄庁による指導監督の機能強化、国・都道府県・市の連携 等
今後、都道府県からの経営介入が更に深まる、とも読み取れそうな内容が数多く散見されています。
「拙速」に注意しつつも、早め早めの情報収集と準備が必要
本法律の通過に基づき、今後、より詳細な細則等もどんどん
形成されてくると思われますが、いずれにせよ、社会福祉法人
に対する大きな改革が「本格的に始まった」ことは、しっかりと認識する必要があると思われます。
前でも触れましたが、多くの事業者にとって、適切な評議員の
探索・人選や会計監査対応、情報開示体制の整備、
社会福祉充実残額の明確化等、求められている仕組に対応して
いくだけでもかなりの労力が費やされる
(=コスト高になる=収支差が益々圧迫されることになる)状況に陥ることは間違いありません
(勿論、従来よりしっかりとマネジメントが出来ている法人にとっては、要求されているレベルはそれほど高くないとも感じられるかもしれませんが)。
2015年度の改定により報酬も大きく低減された中(しかも次期以降も更に厳しくなることが予測されている中)、
このようなコストを如何に吸収しながら、経営の舵取りを行っていくか?或る意味、
自由度が高い一般の営利法人とは質の異なる「難しさ」が、今後の社会福祉法人の経営には覆いかぶさってくると言っても
過言ではありません。
その意味でも、社会福祉法人の経営陣の皆様は国レベルの動きは
勿論、自社が展開する地区の方針や温度感等についてしっかり
情報収集を行うと共に、行政情報のみに翻弄されることなく、
自社の理念に基づいた「あるべき姿」も見据えつつ、
他法人の事例も参考にしながら、自社のビジョンを早期に
描いていく必要があるでしょう。是非、頑張っていただきたいと
思いますし、有益な情報が入り次第、皆様にお伝えさせて
いただくように意識してまいります。
みなさん、こんにちは!
今月の11日神戸市が、介護保険事業の
アミューズメント型デイサービスに関する
“規制”
を打ち出しましたね。
神戸市のホームページには、
次のような文言が掲載されていました。
“介護保険事業のアミューズメント型デイ
サービスの規制”
↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【その1:背景】
介護保険制度は、利用する高齢者が
「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう必要な保健医療サービス
及び福祉サービスに係る給付を行う」
と規定しています。
サービスのひとつである通所介護(デイサービス)とは、
入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び
助言、健康状態の確認その他の居宅介護者に必要な日常
生活上の世話と機能訓練をおこなうこと(施行規則
第10条)と定められており、
提供するサービス内容も、様々な形態が認められて
います。
通所介護(デイサービス)を提供する事業所は、
神戸市に指定権限があり、
厚生労働省令及び神戸市条例で定められた
「人員、設備及び運営に関する基準」
を満たせば指定することができます。
近時、介護保険における通所介護(デイサービス)は、
多様なサービスを標榜した事業が展開されており、
なかでもパチンコ、麻雀、カードゲーム等の遊技を
主な介護サービスとするアミューズメント型デイ
サービスなども出現してきています。
【その2:アミューズメント型デイサービスとは】
アミューズメント型デイサービスとは、
ルーレットやトランプのような娯楽性のある設備を
使って介護予防を図る通所介護(デイサービス)です。
サービスの提供方法も様々であり、
一日の内時間を決めてゲーム等を楽しむ通所介護
(デイサービス)や、
一方、終日ゲーム等を楽しむ通所介護(デイサービス)
もあります。
【その3:アミューズメント型デイサービスの問題点】
とりわけ機能訓練室内にパチンコ、麻雀、カードゲーム
等に特化した設備を備え遊技場の様な雰囲気の中で、
遊技を機能訓練の常時主体とする通所介護(デイサービス)
は、
介護保険法に基づく本来の趣旨にそった適正なサービス
とは考えられず、
アミューズメント型デイサービスの適切な運営を図る
必要があると考えています。
【規制が必要と考える理由】
1)遊技を常時主体とした機能訓練の不適切
通所介護は、利用する高齢者等の尊厳が保持される
形で、
利用者が有する能力を活用して在宅の生活を営むこと
を支援するための機能訓練や日常生活上の世話を行う
ものであり、
遊技を常時主体とするものは、
適正なサービスであるとは考えられません。
2)疑似通貨等の使用が、射幸心、依存性を著しく高めるおそれ
遊技における疑似通貨等の使用は、
もっぱら利用者の射幸心をそそることで遊技を主体とする
機能訓練に動機付けを与えるものであり、
過剰で不必要な介護サービスにつながるおそれが
あります。
3)賭博又は風俗営業等を連想させる広告の危険性
風俗営業等に使用される名称や事業内容等と誤認
するような広告等は、
介護保険による本来給付の趣旨に反し、
かえって善良な風俗環境等に障害を及ぼすおそれが
あります。
【その4:条例改正の必要性】
上記の問題点に加え、
介護保険は保険料と公費を財源として運営されており、
過剰で不必要な介護サービスは、保険料の上昇、
利用者の自己負担の増加につながることなどから、
通所介護(デイサービス)の事業に一定の規制を行なう
ために、
条例改正案を9月市会に提案したいと考えており、
パブリックコメントを実施します。
【その5:パブリックコメント】
1)概要
通所介護(デイサービス)事業者に対し、
以下の内容を規制します。
・
日常生活を著しく逸脱して遊技を利用者に行わせること
・
疑似通貨等、射幸心を著しくそそり、依存性が著しく強く
なるおそれがあるものの使用
・
賭博又は風俗営業等を連想させる名称又は内容の広告
2)実施期間
平成27年8月14日~平成27年8月30日まで
※引用元サイトはこちら
↓
http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2015/08/20150811133301.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一言で言うと、
“度を越した”
デイサービスが出てきてしまった、
ということなのでしょうね。
ただ、「楽しむ」というキーワードは
今後ますます重要になってくるものと思います。
特に、自宅にこもりがちの男性高齢者を
元気にするツールとしては、とても意義のあるもの
ように思います。
ただ、ビジネスでは、その「目的」や「バランス」感覚
をもちながら、すすめていくことは重要であり、特に
制度ビジネスである我々の業界では、このことを
改めて認識しなければならないということを
感じさせる記事でした。
それでは。
みなさん、こんにちは!
今日のブログタイトルは
「自分が変われば人は変わる」。
人間力向上研修でも必ず、皆さんに
お伝えしている内容です。
いつもご紹介している雑誌「致知」
に、このテーマで書かれた
インタビュー記事が
ございましたので、皆様にも
ご紹介したいと思います。
■■□―――――――――――――――――――□■■
北海道札幌市内で創業50年を超える
美容室を経営してこられた宇山照江さん。
そんな宇山さんが苦心の中から
掴まれた人を育てる指針とは――。
「自分が変われば人は変わる」
宇山照江氏(ウマヤ会長)
※『致知』2015年9月号
連載「第一線で活躍する女性」より
□□■―――――――――――――――――――■□□
――ご自身の支えになったものは何ですか。
やっぱり信念というか、
せっかく夫や義父に無理を聞いてもらって出した
お店を絶対に閉められないという思いですよね。
それと母が田舎で農業をしていたので、
早く楽にしてあげたかったんです。
あるお取引業者さんから、職業婦人は、
家庭をさておいて仕事ばかりに
熱を上げるというのでは成功者とは言えないんだよ、
と言われたこともいつも頭にありましたね。
――美容室の運営で辛かったことはありますか。
スタッフの教育がやっぱり大変でしたね。
素直な子もいれば、なかなか言うことを
聞いてくれない子もいる。
親御さんが文句を言ってこられることもあって、
もういろいろですから。一つ屋根の下で、
24時間一緒の暮らしだったので、
息を抜く場所も時間もなくて、
ストレスから膀胱炎になって、
血尿に10年間苦しみました。
――どのように乗り越えてこられましたか。
美容専門の経営コンサルタントの
大津栄五郎先生のご指導を
受けるようになったのが転機になりました。
先生から、
人を変えることはできない。
だけど、自分が変われば人は変わるって習ったんです。
ああ、なるほどと思って、
それから自分を変える努力をするわけです。
――具体的にどんなことを心掛けられたのですか。
例えば、スタッフが挨拶しなくても、
こちらから「お早うございます」と挨拶し続けると、
ちゃんと返してくれるようになる。
集金の人に「ご苦労様」ってお茶をお出ししていると、
スタッフも率先してやってくれるようになる。
あぁ、自分が変われば人は変わるというのは、
こういうことなんだなぁと実感しましたね。
■■□―――――――――――――――――――□■■
いかがでしょうか?
よく「変えることができるのは、自分と未来だけ。
過去と他人を変えることはできない」といいます。
自分が変わることで、相手が変わる。
この「鏡の法則」を是非、皆様にも
実感として感じて頂きたいと思います。
みなさん、こんにちは!!
皆さんは「年輪経営」という
言葉はご存じでしょうか。
「急拡大を求めず、年輪のように
毎年少しづつ 着実に成長を
していき、企業の永続的な存続
を目指す」それが年輪経営です。
昨日は、長野県の伊那市にある
伊那食品工業に大学院のゼミ仲間で
視察に伺いました。
伊那食品工業とは、みなさんおなじみの
「かんてんぱぱ」で
有名なカンテンメーカーです。
今回は、この会社の塚越会長との面会が
かなうという言うことで、大変貴重な時間
を過ごして参りました。
塚越会長の「年輪経営」はあまりに有名ですが、
今回はその年輪経営に込めた真の意味、そして
「トヨタ自動車」が、この年輪経営に学び、
最大の企業価値を「永続的な発展」にされ
ていること、さらには、
「尊敬される会社とは」
「公益資本主義とは」について、
塚越会長とトヨタ自動車の豊田社長との
会談でのエピソードを交え、お聞かせ
いただきました。
最後に、「人」のすべての営みの目的は
「幸せになること」。
それは全ての人の権利であり、また義務でもある。
しかし
多くの人は、その前の目的に目が行ってしまう。
「手段」「目的」を冷静に考えることが
できれば、おおのずと、何が正しいのか
を判断する軸が分かるはず。
企業でたとえれば、売り上げ
利益は、従業員を幸せにする
ための手段でしかない。
本当の目的は、「社員とその家族を
幸せにすること」これが、真の目的では
ないか。
塚越会長の一つ一つの言葉からは、
いかに生きるべきか、いかにあるべきか
を深く考えさせていただく切っ掛けを
たくさんいただきました。
大変貴重な時間をいただきました。
みなさん、こんにちは!!
今日は9月の介護経営セミナーの
お知らせです。
【セミナータイトル】
「新設・処遇改善加算に対応する
キャリアパス・人事評価制度の作り方」解説と
魅力ある職場作りを事例で紹介
「人が辞めない職場、人が集まる職場」
4月からの新設された処遇改善加算?取得には「キャリアパス要件」をクリアしなければなりません。ただ実際には、未だキャリアパス要件が未整備といった事業所が多いのではないで
しょうか。そこで今回のセミナーでは、「キャリアパス」の意義・目的・背景について、わかりやすく解説したうえで、今までのキャリアパス構築支援実績から 規模に応じた「キャリアパスの作り方と運用」について事例で解説いたします。
また、後半では、「人が辞めない事業所、人が集まる事業所」と題し、魅力的な職場作りについて、参考事例をご紹介し、そのポイントをわかりやすく解説いたします。
【第1部:新設・処遇改善加算に対応する
キャリアパス・人事評価の作り方】
・なぜ、国はキャリアパスを求めるのか、その狙いとは
・キャリア段位制度を活用した評価制度
・介護人材育成のための人事評価とは(事例紹介)
・処遇改善加算を活用した賃金制度の実際(事例紹介)
【第2部: 魅力ある職場作りを事例で紹介】
・人手不足の現状
・人が辞めない・人が集まる組織の共通点
・新人職員の定着・戦力化への取組について
・取り組み事例のご紹介
日時
●9月15日(火)13:30~16:30かながわ労働プラザ
●9月25日(金)13:30~16:30 新宿産業会館
●受講料
4320円/人(税込)
●問い合わせ・お申込み
ホームページ問い合わせ欄からアクセス願います。
メール問い合わせ mh591008@crest.ocn.ne.jp
携帯電話 070-6518- 8840
皆さん こんにちは!
さて、
“社会福祉法等の一部を改正する法律案”
が、ちょうど1週間前、7月31日に衆議院を通過し、
現在は、参議院審議へと移行していますね。
ご存知の方も多いかと思いますが、
本改正案の概要はこちらになります。
↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-31.pdf
いよいよ、社福の抜本的な改革が始まるの
かな、
とも感じる一方で、
本案の通過と共に、“社会福祉法等の一部を改正する
法律案に対する附帯決議”
というものも同時に示されて発表されていました。
こちらです。
“社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する
附帯決議”
↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な
措置を講ずるべきである。
【一】
社会福祉法人の経営組織のガバナンスを強化するには、
評議員、理事等の人材の確保や会計監査人の導入等、
新たな負担も懸念される。
このため、特に小規模の法人については、
今後も安定した活動ができるよう、
必要な支援に遺憾なきを期すこと。
【二】
いわゆる内部留保の一部とされる
“社会福祉充実残額”
を保有する社会福祉法人が、
社会福祉充実計画を作成するに当たっては、
他産業の民間企業の従業員の賃金等の水準を
踏まえ、
社会福祉事業を担う人材の適切な処遇の確保に
配慮することの重要性の周知を徹底すること。
【三】
事業の継続に必要な財産が確保できない、
財産の積み立て不足が明らかな法人に対しては、
必要な支援について検討すること。
【四】
地域公益活動の責務化については、
待機児童、待機老人への対応など本体事業を優先
すべきであり、
社会福祉法人の役割と福祉の公的責任の後退を
招くことのないようにすること。
社会福祉法人設立の主旨である自主性と社会福祉事業の
適切な実施に支障を及ぼすような過度の負担を求める
ものではないことを周知徹底すること。
【五】
所轄庁による社会福祉法人に対する指導監督については、
一部の地域において独自の取扱いが散見されるとの指摘
もあることから、
国の基準を一層明確化することで標準化を図ること。
【六】
現下の社会福祉施設における人材確保が困難な
状況に鑑み、
介護報酬、障害福祉報酬の改定による影響を注視
しながら、
職員の処遇の実態を適切に把握した上で、
人材確保のための必要な措置について検討を行う
こと。
【七】
社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成
廃止に当たっては、
職員確保の状況及び本共済制度の財務状況の変化を
勘案しつつ、
法人経営に支障が生じないよう、
障害者支援施設等の経営実態等を適切に把握した上で
報酬改定を行うなど必要な措置を講ずるよう検討する
こと。
【八】
准介護福祉士の国家資格については、
フィリピンとの間の経済連携協定との整合を確保する
観点にも配慮して暫定的に置かれたものであることから、
フィリピン政府と協議を進め、
当該協議の状況を勘案し、
准介護福祉士の名称、位置付けを含む制度の在り方に
ついて検討を行い、
所要の措置を講ずること。
【九】
介護職員の社会的地位の向上のため、
介護福祉士の養成施設ルートの国家試験義務付けを
確実に進めるとともに、
福祉サービスが多様化、高度化、複雑化している
ことから、
介護福祉士が中核的な役割及び機能を果たしていける
よう、
引き続き対策を講じること。
【十】
介護職員の処遇については、
正規・非正規、フルタイム・パートタイム等にかかわらず、
均等・均衡待遇を確保するよう努めること
内容的には、既に議論されている論点をまとめられた
ものですが、今後の社会福祉法人の運営には
大きな影響を及ぼすものと推察いたします。
今後とも引き続き情報を発信していきたいと
思います。
皆さん、こんにちは!
昨年から今年にかけて話題になった
介護コンビニ(「ローソン」)。
この8月に2号店が出店されることが
発表されましたので、皆さんにも
ご紹介いたします。
↓↓↓
株式会社ローソンは、
2015年8月5日(水)に、
株式会社ウイズネット(埼玉県さいたま市)
が、フランチャイズ(FC)オーナーとなる居宅介護
支援事業所とサロンスペースを併設した、
ケア(介護)拠点併設型店舗の2号店
「ローソンさいたまシティハイツ三橋店」
(埼玉県さいたま市)
をオープンいたします。
ローソンは高齢化や健康意識の高まりを受け、
社会変化に対応した次世代コンビニモデルの
構築に取り組んでいます。
ウイズネットは埼玉県を中心に地域密着型の
幅広い介護サービスを展開しています。
ローソンとウイズネットは、
お互いの持つ専門性を生かし、
2015年4月に埼玉県川口市にケア拠点併設型
店舗1号店となる
「ローソン川口末広三丁目店」
をオープンしました。
同店舗では、コンビニの標準的な商品に加え、
介護食や小分け惣菜、生鮮品、米菓・和菓子などを
品揃えし、
シニア・ご家族の方々を中心にご利用いただき
大変ご好評頂いております。
今回オープンする2号店には、
1号店同様、
ウイズネットが運営する介護相談窓口・専用相談室
を備えた
「居宅介護支援事業所」
を併設いたします。
また、自治体関連情報や地域イベント、
介護予防関連の情報を提供し、
地域の皆さんが交流できる
「サロンスペース」
を1号店の倍の広さ確保し、
健康関連の測定機器を設置いたします。
サロンスペースでは、
ヘルスケアに関連したイベントを定期的に
実施していく予定です。
ローソンは、都市部を中心に地域に密着した
介護事業者と連携し、
2017年度末までに30店舗のケア(介護)拠点
併設型店舗出店を目指してまいります。
※引用元サイトはこちら
↓
http://www.lawson.co.jp/company/news/106378/
今後 全国的な広がりができると、地域の
高齢に朗報であるだけでなく、新しい
介護ビジネスとしても注目されるような
展開を期待したいと思います。