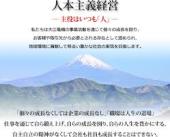ブログ
皆さん こんにちは!!皆様へのお知らせが遅れましたが、
キャリア段位制度の申込が延長になった
ようですね(~6月11日(水))。
「申込をうっかり忘れていた」
「ドタバタしていて申込出来なかった」
という皆様は、チャンスですので、
是非、ご確認下さい!
アセッサー講習の追加募集はこちら
↓
https://careprofessional.org/file/tuika-a0527.pdf
外部評価審査員講習の追加募集はこちら
↓
https://careprofessional.org/file/tuika-s0527.pdf
以上、取り急ぎのご連絡まで。
何かのお役に立てれば幸いです。
皆さん、こんにちは!!
今日は、日ごろ人間力研修で
お伝えしている「人間力を高めるには」
の部分をお話ししたいと思います。
人間力の高い方の特徴の一つに
「当たり前のことを当たり前にできる」
という共通点があるように感じます。
人間力を高めるには、何か特別な事を
しなければならないわけではなく、
当たり前のことを、当たり前のように
しっかりと行う。
でも、実は、これって毎日、意識をして
行動していないと、意外に出来ないものです。
教育哲学者の森信三先生が説かれていた
「しつけの三大原則」について書かれた
雑誌「致知」の内容をご紹介いたします。
※『致知』2014年6月号
連載「致知随想」より
「しつけの三大原則」
帆足行寿(NPO法人福岡実践人顧問)
└───────────────────────┘
「森信三という素晴らしい教育哲学者がいる」
そんな話を伝え聞いたのは昭和52年、
私が福岡の教育委員会で指導主事を務めていた時でした。
当時は全国各地に校内暴力の嵐が吹き荒れ、
教育の荒廃が深刻化していました。
私の地元でも、生徒がトイレを壊したり、
教室のガラスをたたき割ったりするような中学校が何校もあり、
教育をいかに基本から立て直すかということが
喫緊の課題になっていました。
森先生が福岡の仁愛保育園で
母親を対象にお話をされると聴いた私は、
早速聴講させていただくことにしました。
驚いたのは、そこでは大の哲学者が、
「呼ばれたら大きな声で“はい”と返事をしましょう。
“はい”という返事が人間の我を断つのです」
と、実に単純極まりないことを
熱心に説かれていたことです。
「腰骨を立てましょう。
腰骨イコール主体で、
腰骨を立てない限り真の人間にはなれません」
「しつけの三大原則というものがあります。
一、朝のあいさつをする子に
二、「ハイ」とはっきり返事のできる子に
三、席を立ったら必ずイスを入れ、
ハキモノを脱いだら必ずそろえる子に」
人間をつくっていく上での基本を見事に捉えたお話に、
目から鱗が落ちる思いがしました。
人生を変える出逢いを果たしたのは、
師が82歳、私が47歳の時でした。
衝撃を受けた私は、入手困難だった森先生の全集25巻を
東京の古書店に求め、当時のお金で40万円の大枚をはたいて入手しました。
そこに記されていた言葉は一言一句が強烈に心に響き、
重要と思われるところに朱線を引きながら
再読を繰り返すうちに、全文真っ赤に染まりました。
また、森先生が来福される度に私は案内役を務め、
ご講演先に随行して先生の教育哲学を一所懸命に吸収しました。
いかがでしょうか?
まさに人間が生きる上での「基本」を
説かれているものと思います。
当たり前のことを当たり前にする
ことで、最後は「自分のこころ」が
磨かれ、結果として自らの人間力が
高まってくるものと思います。
⇒福祉人材の人間力向上研修
皆さん、こんにちは!
昨日の新聞で、こんな記事を
見つけました。内閣府が調査した
若者意識調査の結果です。
『内閣府が世界7か国の13歳から29歳
の男女を対象に実施した意識調査で
自国のために役立つことをしたい
と答えた日本の若者は54%にあたり
7か国中、トップだったことがわかった。
一方、自分自身に満足して
いると答えた割合は日本が最も少なく、
社会貢献したいのに自信が持てない
若者の姿が浮かび上がった。
自分自身に満足してるでアメリカは
86%韓国72%に対し日本は68%で
最下位だった』
人間力研修では、福祉のこころで
大切な「利他こころ」と「自己反省の
こころ」をお伝えしています。
多くの介護職の方々の反応をみていると
まさに、この調査結果が当てはまります。
介護職の皆さんは、どなたも「利他のこころ」
をお持ちです。いつも人の役に立ちたい、という
想いで、お仕事に取り組んでいらっしゃいます。
おそらく、人一倍「利他のこころ」をお持ちの
方が多いと思います。
又、職場や私生活で何か、失敗したり、壁に
ぶつかったりすると、自分をまず責めてしまう
方が多いようにも感じます。
でもこれは「自責」であった「反省」
とは違いますよね。
「自己反省」とは、自分を責めるのでは
なく、自分の行動を前向きに振り返る事
を言います。
失敗しない人間などいません。
失敗した時は、「なんで自分はダメなんだろう」
と思ってしまうことってありますよね。
わたしも、よくそう思っていました。
でも、よく考えてみてください。
自己否定や自己嫌悪して、何かいいこと
ありますか?誰かが喜びますか?
結局は、自分が暗くなるだけですよね。
そもそも他人は、あなたが失敗をやらかした
ことすら、忘れてしまってるかもしれません。
結局は、自分の「こころの置き方」ひとつなのです。
自分のこころを切り替える。
これも「訓練」だと思います。
そう「スキル」なのです。
だれでも、訓練さえすれば、
自分のこころの置き方は
変えられるものです。
そんなことを、人間力研修でみなさんに
お伝えしております。
人間力研修とは・・・
福祉人材の人間力向上研修
「質の評価に関する調査研究事業」のポイントをおさえておきましょう。
2006年(平成18年)以降、社会保障審議会介護給付費分科会における今後の課題として明確に位置付けられた「介護の質の評価」。平成21年(2009年)には質の評価に関する検討委員会が設置されました。
また、最近、私たち介護業界でも話題になっている「産業競争力会議」では、質の評価について、次のような言葉が示されています(下記は、産業競争力会議 医療・介護等分科会 中間整理資料より抜粋)。
「介護サービスの質の改善に向けては、最終的には事業者毎のサービスの質の評価を利用者に提供すると同時に、サービスの質の評価を活用した介護報酬制度の改革を行い、質の改善に対するインセンティブを付与することを目指すべきである。このため、まずは、サービス種別や運営形態の特性を踏まえた質の評価に向けた仕組み作り(評価対象施設や評価項目・分析手法などの評価手法、情報公開等)について、平成26年度末までに検討し、その結果を公表する。」
今後、社会保障財政が益々厳しさを増す中で、費用対効果、即ち、「質の高い事業者に限りある財政を投入し、有意義な介護機能を確立する」という方向性が強まることは、当然と言えば当然と言えるでしょう。そこで、今回のブログでは、同テーマに関する現時点のポイントについて、確認しておきたいと思います。
「質の評価」に関しては、第81回介護給費費分科会(2011年(平成23年)10月7日)において、次のような指摘が為されており、その考えは現在も踏襲されています。
○介護サービスは、施設サービスと居宅サービスに大別されるが、施設サービスについては基本的にほぼ全てのサービスが単一事業所により提供されていることから、施設入所者の状態等は当該施設のサービス提供の結果とみなすことが可能である(※アウトカム評価が可能、という意味)。
○一方、居宅サービスについては、サービス提供事業所が複数にまたがること、地域ごとの事業所整備状況やケアプラン、家族によって提供される介護も利用者の心身の状況等に一定の影響を与えることから、個別の事業所単位ごとのサービスの質の評価が困難である
(※ストラクチャー評価、プロセス評価を中心に据えるのが合理的である、という意味)。
上記視点に基づき、先ずは「質の評価」に関してモデルが構築しやすい(国内に先進事例が存在する、という意味で)「老人保健施設」「通所介護」「居宅介護支援」の3サービスが取り上げられ、評価指標の構築が進められています。まだ検討過程であるため、これ以上の言及は差し控えますが、先ずは、
?質の評価は「ストラクチャー」「プロセス」「アウトカム」の視点に基づいて進められること、
?3つの視点については、サービスによって比重が変わってくること、
以上2点しっかりとおさえておいていただきたいと思います。
(更に詳しい情報をお求めの方は、下記URLにアクセスして内容をご確認下さい)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000042450.html
今後、介護報酬の上昇に期待が持ちにくい中、質の評価によるインセンティブは、経営的に大きな武器になる可能性もあるでしょう(自社の質を高めるという意味でも、顧客へのアピール、という意味でも)。今、既に存在しているインセンティブの切り口(体制加算etc)も含め、是非、このタイミングから、「介護サービスの質を高める」ことに対し益々真剣に捉えると共に、如何にして「質に対する自らの価値観」と「国からのメッセージ」を両立させるかについて、柔軟に考えていくべきではないでしょうか。
我々としても今後、本テーマに対して新たな情報が入り次第、皆様にもご報告をさせていただきますが、是非、現段階でも検討・準備を進めることが出来るであろう内容については、早めに社内で議論を進めておくことをお奨めします。
みなさん こんにちは
今日は、メンタルヘルスの問題
についてのお話です。
メンタル問題の要因の多くは
極度なストレスと言われます。
このストレスを軽減することが
できたら、と職場のリーダー
はいつも考えているのでは
無いでしょうか?
例えば、残業時間を減らせば
ストレスが減るわけではない
と言われますが、実際に仕事量を
減らさずに、人も増やさずに、
心の問題を減らすことができる
のでしょうか。
ある会社の研究者と事務職で仕事内容
とストレスを比べたデータがあります。
研究者の方が、仕事の量的負荷、質的負荷は
強く感じているものの事務職よりも
ストレス反応が低く、心身の健康に良好だ
という結果が出ました。
それは、研究系は、自分のベースで
仕事が出来るという裁量権や達成感
(仕事をやり遂げたときの満足感)で
ストレスを緩和する要因が大きく、
量と質のストレスを打ち消すという事が
実証されています。
つまり、皆さんのマネージメントによって
部下のストレスの感じ方は大きく
変わってくるのです。
キーワードは
【裁量権」と「達成感」】です。
これがラインケアの大きなポイントであると
思います。
つまり、実際に仕事量を減らさずに、
人を増やさずに、心の問題を減らすことはできるのか、
これには、何か特別なことをしなければならない
のでなく、部下がやりがいを持ちながら、
力を発揮できる職場環境作りが必要と
いう事になるのです。
いかがでしょうか?
何かのご参考になれば幸いです。 みなさん こんにちは!!
今日はチームワーク作りに必要な
リーダーの役割について考えて
みたいと思います。
みなさんの職場でチームの一体感を
創り上げるには、どこからスタート
すればいいのでしょうか?
チームみんなで飲み会やリクレーション
などをする事でしょうか?
それは、それで、コミュニケーション環境
を創るには とても大切な事だとは
思います。
ただ、チームワーク創りから考えるのでは
なく、まずは、「上司―部下」という
1対1の信頼関係づくりから始める事が
必要であるように思います。
リーダーであるあなたと
部下一人一人の絆を
まず創り上げる事。
これがチームワークの初め一歩になります。
つまり自分と職員A、自分と職員B、
自分と職員Cの信頼関係づくりです。
すると上司が核となり、今度は横の
繋がりが出来始めます。まずは
上司であるあなたが、部下との絆を
作ることで、部下一人を満たす努力をする。
これによって部下の心は安心で満たされ
「誰かをたすけよう」と気持ちが抱ける
だけの心の余裕が生まれるのです。
そして、この上司のためにがんばろうという
同じ思いの元に職員同士が団結します。
これがチームワークへ育っていくものと
思います。
いかがでしょうか?
何も特別な事ではなく、当たり前の事
ですよね。
でも、それによって自然に
チームワークがつくり上げられて
いく、そんな気がします。
何かのご参考になれば
幸いです。
⇒職場リーダー(主任)の職場実践力&人間力向上研修
皆さん、こんにちは!!
昨日は5月に入り、3度目の
介護経営セミナーでした。
今回のテーマは、「人事評価と給与制度」
です。
来年からの介護保険法改正を見据え、
これから益々厳しさを増すであろう
介護報酬のなかで、給与の総額を
どのようにコントロール、また
どのような考え方で職員に分配して
いくべきなのか、
それが今回のセミナーテーマ
でした。
今回は、たまたまですが、
神奈川県下の介護事業所の方々に
数多くお集まり頂き、
開催させて頂くことが出来ました。
また、セミナーの内容的には、かなりの
ボリュームとなってしまい・・・
多少不安でしたが、概ねみなさん
満足されて聴いていただけた
ようなので、すこし、ほっとしています。
また、来月以降も、引き続き開催
していく予定ですので、
皆様、御時間があるときにご参加
下さい。
来月以降のスケジュールとテーマ
は、またブログにてお知らせ
致します。
みなさん こんにちは。
今日は、人本主義経営について
考えてみたいと思います。
まず、あまり聞きなれない
人本主義という言葉。
資本主義が「お金」主体の経営
であるならば、人本主義は「人」
が主体の経営です。
何が違うのか?簡単に言うと
資本主義は「売上、利益、株主配当」
がその目的であるのに対し、人本主義は
「人の幸せ」をその目的とします。
つまり「人が幸せ」になれば、必要な
利益は後からついてくるという考え方です。
また、ここでいう「人」とは「従業員と
その家族」「取引業者とその家族」さらには
「地域の方々」を含みます。
今の日本の中小企業では、「資本主義」から
「人本主義」に舵取りを変える企業が増えて
います。なぜなら、企業で抱えるほとんどの
課題が「人」に関する問題だからです。
逆に言えば、「人」に係る課題を解決
することで、企業のほとんどの問題が
クリアできる事になります。
人本主義経営が浸透している組織の
特徴は、「企業理念」を大切にしている事。
そして、それを日常の行動に落とし込んでいる事。
そして、そこには、とても強い「こだわり」
があること。二つ目は、経営者の理念を
理解し、それを浸透させるリーダーの存在
があること。三つ目が、従業員はみな家族
という絆で繋がっており、その成長を心から
喜ぶことが出来る風土を持っている事。その
ための社員のこころを育てる教育や人間力
を高める教育をしている事。
その結果として、人が集まる組織になる、
つまり「お客様」「従業員」の双方が・・・・
すると、当然ながら、業績が向上する・・
そして、さらにこのようなサイクルが
回り始めると、景気に影響されることなく
会社が発展する。なぜなら、お客様に
選ばれる会社になっているからです。
いかがでしょうか?
このような「経営改革」の流れこそ
われわれ介護業界の今に必要とされて
いるものだと思いませんか?
一般企業でいう景気の影響は
介護業界でいう、「保険法の改正」
に該当します。法律がいかに変わろうと
介護の本質は変わらないはずです。
これからの介護業界は新しい
時代を迎えようとしています。
新しい時代に合った介護経営
を考えてみませんか?
この経営にご興味のある方は
ご連絡ください。
具体的な情報をご提供させて
頂きます。
みなさん、一緒に新しい介護業界
を創り上げていきましょう。
介護人間力向上研修とは
福祉人材の人間力向上研修
みなさん、こんにちは。
先週の土曜は、久々に大阪での
お仕事でした。
午前中は保育士さんの
リーダー研修。
保育園の園長や主任そして
これからの主任候補の方、
それぞれにお集まり頂きました。
この研修は大阪市からの受託事業
で、大阪市の保育士さんの確保と
育成を目的にした市の事業です。
保育士さんの育成、定着率の向上には
リーダーとして、どうあるべきなのか。
それがこの研修のメインテーマです。
そして、具体的に職場でどのように
活かすことが出来るのかを、学んで頂く
ことがゴールです。
みなさん、とても熱心に受講
頂き、『とても勉強になりました』
『職場に戻って活かします』
とのお声を頂き、むしろ、こちらから
から感謝したい気持ちでいっぱいに
なりました。
そして午後は、大阪の介護事業主
向けセミナーです。
テーマは『職員の採用』『人事制度』
についてお伝えしました。
昼食を挟み、6時間の講義でしたが
みなさんの熱心さに、息つく暇も
無く、頑張らさせて頂きました。
みなさん、本当にありがとうございました。
そして次回の7月にまた元気で
お会いしましょう。
リーダー研修はこちらから
→
職場リーダー(主任)の職場実践力&人間力向上研修 みなさん、こんにちは!
本年度の介護人間力研修が、
昨日スタートしました。
今年度は、埼玉県の特養
さんからのスタートです。
昨日は、同法人の4事業所
から介護職の若手25名に
お集まり頂き、研修会を
実施いたしました。
今回の研修では、
皆さん一様に、研修で、
何かを摘もうと、強い
目的意識をもって、
受講されているなぁ、と
改めまして感じました。
その前向きな、目的意識と
熱心さがヒシヒシと伝わって
きました。
そして、終了後のアンケート
を拝見すると、「介護職として
働く意味をこれから自分の中で
良く考えてみたいと感じました」
「これからの研修が楽しみです」
等など。多くの前向きなご意見と
ご感想を頂きました。
6月~特養さん、老健さんを中心に
5施設で研修会がスタートし、
県社会福祉協議会では埼玉県、
茨城県にて秋にかけて
研修が始まります。
多くの施設の「活き活き職場つくり」に
そして、一人でも多くの職員の方々の
笑顔が見られるように、今年も
がんばります。
介護人間力向上研修とは
→
福祉人材の人間力向上研修