介護
厚生労働省が1月30日に新たに公表した介護経営の「協働化・大規模化ガイドライン」。この中では、法人の合併やM&Aといったハードルの高い手法だけでなく、中小の事業者が独立性を保ちながら経営課題を解決する「協働化」の重要性と、その実践的なノウハウが詳しく紹介されている。
介護ニーズの変化や深刻な人材難、物価の高騰、賃上げ競争の激化、制度の複雑化、生産性の向上…。経営課題が幾重にも重なるなか、個々の事業所・施設が独力でサービスを安定的に維持していくことは、かつてないほど難しくなっている。
今回のガイドラインでは、地域の事業者が協働化を通じてスケールメリットを得るための選択肢が提示されている。ガイドラインが提唱する協働化のファーストステップは、「仲間をつくる」ことだ。
必ずしも最初から緻密な設計図を描く必要はない。
ガイドラインで紹介されている社会福祉法人東北福祉会(仙台市)の事例では、業界団体の会合などを通じて元々つながりのあった法人同士が、協定書や契約書を作成しないまま、必要な各種研修の共同開催を実現したという。お互いの事業所を見学し合い、課題認識を共有するという「日常的な関わり」の延長線上で、各種研修のマンネリ化や講師の固定化の解消、満足度の向上、人材の定着といった成果を生み出した。
その結果、地域内で経営課題を率直に共有・相談できる環境が構築され、赤字から黒字への転換など具体的な経営改善につながっている。今後については、「より実践的な方向性へ移行したい」。事務作業や人材育成の協働化も含め、「人的・時間的・資本的なリソース不足を補っていければ」との前向きな言葉が寄せられている。
個々の事業所の状況に合わせて、まずは身近な仲間づくりから始めてほしいと呼びかけている。
厚労省はガイドラインで協働化の効果について、人材確保・育成の合理化や事務作業の効率化、コストの削減、災害対応の強化などに加えて、「法人の交流を通じた知見やノウハウの共有が、結果として事業所・施設の経営改善にも寄与する」と指摘した。そのうえで、個々の事業所の状況に合わせて、まずは身近な仲間づくりから始めてほしいと呼びかけている。
2025年12月25日「介護保険制度の見直しに関する意見」が上梓
2025年12月25日の介護保険部会にて提示された、「介護保険制度の見直しに関する意見」(以下、「本資料」という)。本部会では2027年度介護保険法改正・報酬改定に向けた論点整理、及び視点の提示が行われています。今回の本資料の特徴は何と言っても「ページ数が多い」こと。3年前は42ページでしたが今回は何と、67ページと25ページも増えており、1回のニュースレターでは採り上げづらいボリュームになっています。そこで今回は、今年から新たに方針が示された地域3分類(中山間・人口減少地域、大都市部、一般市等)の内容に絞り、特に中山間・人口減少地域に対する論点を中心に採り上げてお伝えしてまいります。
「介護保険制度の見直しに関する意見」地域3分類に関する論点とは
それでは早速、中身に移ってまいりましょう。先ずは中山間・人口減少地域における柔軟な対応等に関し、「特例介護サービスの枠組みの拡張」についてです。
◯地域の実情に応じてサービス提供体制を維持・確保するため、人材確保、ICT機器の活用等の生産性向上の方策など、自治体が必要な施策を講じた上で、それでもなおやむを得ない場合、中山間・人口減少地域に限定した特例的なサービス提供を行う枠組みとして、特例介護サービスに新たな類型を設けることが適当である。
◯この新たな類型においては、
・職員の負担への配慮の観点から、職員の賃金の改善に向けた取組、ICT機器の活用、サービス・事業所間での連携等を前提に、管理者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等を行うこと
・サービスの質の確保の観点から、市町村の適切な関与・確認や、配置職員の専門性への配慮を行うことを前提とすること
が考えられ、今後、詳細な要件について、介護給付費分科会等で議論することが適当である。
なお、これらの要件が自治体で厳しく解釈されると、必要な配置基準の緩和が進まなくなるのではないかとの意見があった。
◯新たな類型の特例介護サービスについては、現行の基準該当サービス・離島等相当サービスの対象となっている居宅サービス等(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援等)に加え、施設サービスや居宅サービスのうち特定施設入居者生活介護も対象とすることが適当である。また、市町村が指定権者となり実施している地域密着型サービスにおける同様のサービスについても、同様の対応を実施できるようにすることが適当である。
◯なお、新たな類型の特例介護サービスについては、
・サービスの質の担保について、事後の確認を行う仕組みについても検討が必要ではないか
・介護保険制度は全国どこでも必要なサービスを提供すべきものであり、配置基準の緩和は、慎重に対応するものとして、あくまでも緊急的な対応として行うものとすべきではないか
・ICT機器の活用などの業務効率化の取組は、必要人員を代替し得るものであるかどうか精査が必要ではないか
・まずは現行の居宅サービス等に限定し、施設サービス等を対象に含めるかどうかについては、ICT機器等の活用実績を踏まえ慎重に検討すべきではないか
・夜勤要件の緩和については、特に職員の負担感などへの配慮が必要ではないか
との意見があったことにも留意し、今後詳細な要件について、介護給付費分科会等で議論することが適当である。
続いて、「地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み」についてです。
◯中山間・人口減少地域においては、利用者の事情による突然のキャンセルや利用者宅間の移動に係る負担が大きく、また、高齢者人口の減少に伴うサービス需要の縮小、季節による繁閑の激しさ等から、年間を通じた安定的な経営が難しく、サービス基盤の維持に当たっての課題となっている。
◯このため、特例介護サービスの新たな類型の枠組みにおいて、安定的な経営を行う仕組みとして、例えば訪問介護について、現行のサービス提供回数に応じた出来高報酬と別途、包括的な評価(月単位の定額払い)を選択可能とすることが適当である。
◯こうした包括的な評価の仕組みについては、
・利用者数に応じて収入の見込みが立つため、特に季節による繁閑が大きい地域や小規模な事業所において、経営の安定につながる
・移動時間など、地域の実情を考慮した報酬設定が可能となるほか、突然のキャンセル等による機会損失を抑制し、予見性のある経営が可能になる
・利用回数や時間の少ない利用者を受け入れた場合でも、収益が確保できる
・安定的かつ予見性のある経営が可能となることで、常勤化が促進されるなど、継続的かつ安定的な人材確保につながる
・利用者の状態変化により利用回数や時間が増えた場合でも、負担が変わらず、安心感がある
等のメリットが期待される。
◯その一方で、
・利用者ごとの利用回数・時間の差にも配慮しながら、利用者間の不公平感を抑制する必要がある
・利用者の費用負担が急激に増えることや、区分支給限度基準額との関係でサービス利用に過度な制約がかからないよう、適切に配慮を行う必要がある
・保険料水準の過度な上昇を抑制する観点や、対象地域の内外での報酬水準の均衡等も踏まえて、サービス提供量と比べて過大な報酬とならないようにする必要がある
・利用回数や時間にかかわらず一律の報酬となることにより、利用者が必要以上にサービスを利用する、事業者が必要なサービス提供を控える、といったモラルハザードを抑制する必要がある
といった点に十分な留意が必要である。
◯このため、具体的な報酬設計については、利用者像ごとに複数段階の報酬区分を設定することや、区分支給限度基準額との関係性にも配慮しつつ包括化の対象範囲を設定するなど、きめ細かな報酬体系とする方向で検討を進める必要がある。こうしたことも踏まえて、報酬水準の設定に当たっては、現状の十分なデータ分析の下、包括的な評価の仕組みを導入する事業者の経営状況や、サービス提供状況等に与える影響を考慮しつつ、今後、介護給付費分科会等で議論することが適当である。
◯また、ニーズを有する地域の事業者が迅速に対応できるよう、希望する自治体においては、第10期介護保険事業計画期間中の実施を可能とすることを目指し、第9期介護保険事業計画期間中に検討を進めることが適当である。
続いて、「介護サービスを事業として実施する仕組み」についてです。
◯今後、2040年を見据えると、サービスを提供する担い手だけでなく、更なる利用者の減少が進む地域も想定される中、上述のような給付における特例の仕組みを活用しても、なおサービス提供体制を維持することが困難なケースが想定される。
◯こうした地域においても、契約に基づき利用者本位でサービスを選択するという介護保険の制度理念を維持するとともに、利用者が住み慣れた地域を離れ、在宅での生活を継続することが困難となる状況を防ぐことが重要である。
◯このため、こうした場合に備えた中山間・人口減少地域における柔軟なサービス基盤の維持・確保の選択肢の一つとして、給付の仕組みに代えて、市町村が関与する事業により、給付と同様に介護保険財源を活用し、事業者がサービス提供を可能とする仕組みを設けることが適当である。
◯この仕組みにおいては、要介護者等に対して、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等といった給付で実施するサービスを実施できるようにするとともに、こうしたサービスを組み合わせて提供することが考えられる。このようなサービス提供についても、利用者との契約に基づき、適切なケアマネジメントを経て、要介護者に対して介護サービスを提供するという点においては、給付サービスと変わりがない仕組みとすることが適当である。また、本事業は、人口減少社会の中で、被保険者(住民)のために介護サービスを維持・確保することが目的であり、その導入に当たっては、対象地域の特定と併せて、介護保険事業(支援)計画の策定プロセスの一部として、被保険者(住民)等の関係者の意見を聴きながら検討することが想定される。
◯今回の新たな事業の仕組みによる事業費については、例えば、圏域を超えて訪問する際の経費など、中山間・人口減少地域へのサービス提供に係る追加的な費用も勘案することも考えられる。なお、複数のサービスを組み合わせて弾力的に提供するケース等が想定されることを踏まえると、単独の事業所等におけるサービス提供時に要するコストと比べて、一定程度効率的に実施することも可能になることも想定される。
◯その上で、新たな事業は、地域支援事業の一類型として実施することが考えられ、その財源構成は、国、都道府県、市町村、1号保険料、2号保険料ごとに、現行の給付サービスと同様の負担割合とすることが考えられる。
◯中山間・人口減少地域における居宅サービスが継続的に提供されることにより、当該地域における在宅の要介護高齢者が引き続き在宅で生活することが可能となること等を踏まえると、この事業の実施が当該市町村の介護保険財政に与える影響は、施設サービス等の他の給付費を含めて総体的に見ればそれほど大きなものとはならないと考えられるものの、保険財政規律を確保する観点から、当該事業費の総額についても、他の地域支援事業と同様に、高齢者の伸び率等を勘案した上限額を設定することが考えられる。
◯包括的な評価の仕組みと同様、中山間・人口減少地域における事業者の経営やサービス提供の状況等を十分に検証の上、こうした地域において実際に活用可能なものとなるよう、都道府県や市町村の負担軽減の観点も含めて、関係者の意見を丁寧に伺いながら、検討を進めることが必要である。
◯なお、介護サービスを事業として実施する仕組みについては、制度の導入により、市町村に責任が集中することにならないよう、都道府県が一定の関与をする仕組みとするなど、丁寧な検討を行うべきとの意見があった。
最後に、「大都市部・一般市等における対応」に関し、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の統合」についてです。
◯定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護高齢者の在宅生活を24時間支えるサービスとして、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護の両方を提供し、「定期巡回」と「通報による随時対応」を行っており、特に今後増加する都市部における居宅要介護者の介護ニーズに対して柔軟に対応することが期待されている。一方で、夜間対応型訪問介護は、夜間における「定期巡回」と「通報による随時対応」を行うもので、これまでの本部会等の議論においても、両サービスは機能が類似・重複しており、将来的な統合・整理に向けた検討の必要性について指摘があったところである。
◯両サービスの機能・役割や、将来的なサービスの統合を見据えて段階的に取り組んできた状況を踏まえ、また、
・夜間対応型訪問介護の多くの利用者は日中の訪問介護を併用しており、日中・夜間を通じて同一の事業所によって24時間の訪問介護(看護)サービスを一体的に受けられることは、夜間対応型訪問介護の利用者にとって効果的と考えられること
・8割以上の夜間対応型訪問介護事業者が定期巡回・随時対応型訪問介護事業所も運営しており、定期巡回・随時対応型訪問介護事業所にとっては、事業所の指定手続や報酬請求事務等が効率化されるなど、限られた地域資源の有効活用にも資すること
・令和6年度介護報酬改定で設けた定期巡回・随時対応型訪問介護看護の新区分について、利用者に不利益は生じていないと考えられることから、夜間対応型訪問介護を廃止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と統合することが適当である。
◯なお、この際、必要な人員の確保やサービスの認知度向上など、利用者・事業者双方への影響にも十分配慮する必要があることから、一定の経過措置期間を設けた上で、人員配置基準や報酬に関して特例的な類型を設けることが適当である。
タイムリーにキャッチアップしつつも、過度に振り回されないように
以上、今月は「介護保険制度の見直しに関する意見」から一つのテーマに絞り、お伝えしました。今回の資料により、2027年の法改正・報酬改定へ向けての大きな方向性は概ね示されたと思われます。今後の手続きとしては、議論は介護給付費分科会へと引き継がれ、より細かな改正法案・改定報酬案に関する審議が展開されることになります。経営者・幹部の皆様は是非、ご自身でも情報を追いかけていただくと共に、制度の活用は重要である一方、そこにばかり心が奪われ、結果、制度に振り回される、ということがないよう気をつけていただく必要もあるかもしれません。
いずれにせよ2027年の改正・改定へ向け、2026年はさらに具体的な議論が始まります。
我々もしっかりと追いかけ、タイムリーな情報提供を心掛けてまいりますので、引き続きよろしくお願い致します。
※本ニュースレターの引用元資料はこちら
↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001622725.pdf
結論:週休3日制は「魔法の制度」ではないが、正しく設計すれば定着率を高める有効策
介護業界では慢性的な人材不足が続く中、「週休3日制」を導入する事業所が徐々に増えています。
結論から言えば、週休3日制は万能ではありません。しかし、勤務時間設計・給与制度・シフト管理を適切に行えば、
-
採用力の向上
-
職員の定着率アップ
-
離職防止・燃え尽き防止
といった効果が期待できる制度です。
一方で、制度設計を誤ると
「職員の不満が増える」「現場が回らない」「人件費が逆に増える」
といったリスクもあります。
本コラムでは、介護事業所における週休3日制の導入時の注意点を社労士視点で解説します。
週休3日制の成否は、就業規則でも給与制度でもなく、シフトと人員配置の再設計が重要
週休3日制で現場が苦しくなる事業所の共通点
これまで多くの介護事業所を支援してきましたが、
週休3日制がうまくいかないケースには、はっきりした共通点があります。
それは、
**「従来の人員配置のまま、休みだけを増やそうとしている」**ことです。
-
1人あたりの勤務時間は長くなった
-
しかし、時間帯ごとの配置は見直していない
-
結果、忙しい時間帯がスカスカになる
この状態では、どれだけ理念が良くても、現場は確実に疲弊します。
介護の仕事は「人数」ではなく「時間帯」で考えるべき
介護保険制度上、人員配置基準は「常勤換算」で語られることが多く、
つい「トータル人数」で考えがちです。
しかし、現場で起きているのは、
時間帯ごとの負荷の偏りです。
-
朝の起床・排泄・送迎
-
昼の入浴・記録
-
夕方から夜の食事・就寝介助
この“山”の時間に人が足りないと、
事故リスク、職員の苛立ち、利用者満足度の低下が一気に表面化します。
そこで重要になるのが、
**勤務時間が重なる「オーバーラップ時間」**です。
なぜ「重なる時間」がないと、週休3日制は破綻するのか
週休3日制(給与維持型)の多くは、
1日10時間勤務が前提になります。
このとき、
「誰かが来たら、誰かが帰る」
というシフトを組んでしまうと、現場はこうなります。
-
申し送りは紙だけ
-
忙しい時間を1人で回す
-
トラブルが起きても応援がない
これは、**制度以前に“無理な現場”**です。
私が支援に入ったある事業所では、
重なる時間を設けていなかったため、
「休みは増えたのに、勤務中は前よりきつい」
という声が続出しました。
重なる時間が生む「3つの余白」
重なる時間を意図的に作ると、現場に余白が生まれます。
① 業務の余白
一番忙しい時間に人がいることで、
介助・対応の質を落とさずに済みます。
② 判断の余白
「これ、どう対応する?」
とその場で相談できる相手がいることは、
職員の心理的負担を大きく下げます。
③ 人間関係の余白
忙しさを分かち合えることで、
「自分だけ大変」という不公平感が生まれにくくなります。
これは、離職防止の観点でも非常に大きい効果です。
社労士として必ず勧める人員配置の考え方
私が週休3日制の支援で必ず提案するのは、
次のような設計です。
-
1日10時間勤務を前提に
-
開始・終了時刻をずらす
-
2〜3時間以上の重なりを作る
たとえばデイサービスであれば、
-
早番:7:30〜18:30
-
遅番:9:00〜20:00
こうすることで、
**9:00〜18:30という“人を厚くする時間帯”**が生まれます。
ここに入浴・記録・家族対応などを集中させることで、
現場は驚くほど安定します。
週休3日制は「人を減らす制度」ではない
誤解されがちですが、
週休3日制は人件費削減の制度ではありません。
むしろ私は、
**「人を守るための配置転換制度」**だと考えています。
-
ずっと張り付かなくていい
-
1人で抱え込まなくていい
-
無理な我慢をしなくていい
この環境を作れなければ、
どんなに先進的な制度も、現場には根付きません。
まとめ:週休3日制は“設計図”で決まる
介護事業所の週休3日制は、
「導入するかどうか」よりも、
**「どう設計するか」**がすべてです。
特に人員配置では、
-
時間帯別に業務量を見る
-
重なる時間を意図的に作る
-
忙しさを分け合える構造にする
この視点が欠かせません。
週休3日制を、
現場を壊す制度にするか、守る制度にするか。
その分かれ道は、
この「人員配置の再設計」にあります。
介護職員の賃上げに向けて支給する今年度の補正予算による新たな補助金について、厚生労働省が運用ルールの細部を明らかにするQ&A(第1版)を公表した。介護保険最新情報Vol.1462で広く周知している。
厚労省はこの中で、補助金の一部を充てることができる職場環境改善の経費について、パソコンやタブレットなどの購入には使えないとする解釈を明示した。ICT機器などの導入を検討している事業者は注意が必要だ。
厚労省は今回のQ&Aで、職場環境改善の経費の使途を説明。「PC端末などの機器の購入費用は対象経費として適当ではない」との認識を示した。
また、見守りセンサーやインカム、記録ソフトなどの購入費用も対象ではないと改めてアナウンスした。こうした機器の活用に向けては、介護テクノロジーの導入を推進するための補助金を用いるよう促しており、今回の賃上げ補助金では機能・役割を切り分けている。
今回の賃上げ補助金は、介護職員1人あたり最大で月額1.9万円の「3階建て」の設計とされた。事業者はこのうち「3階部分(プラス4千円相当)」を、職場環境改善の経費としても活用することができる。現場の裁量でより柔軟に使える枠だが、今回、その対象経費の範囲に制限があることがクリアになった形だ。
厚労省はあわせて、充当が認められる職場環境改善の経費の例も示している。
具体的には、職場環境改善のための研修や介護助手の募集にかかる費用などが対象となる。また、現場の課題の見える化や委員会の設置、役割分担の明確化といった取り組みを進める経費も認められる。あくまで「人」や「仕組みづくり」への投資が対象で、ハードやシステムに直接振り向けることはできないといった整理になっている。
2026年6月、介護保険制度における 介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」) が大幅に見直されることが決定しました。この改定は、介護現場が抱える深刻な人材不足と賃金水準の低さという根本課題に対応するため、従来の3年ごとの通常改定とは別に 臨時(期中)改定 として実施される異例の政策です。加算の拡充は介護報酬全体の引き上げと合わせて、介護従事者の待遇改善や人材確保に向けた国の本気度を示すものとなっています。
本コラムでは、2026年6月施行の処遇改善加算のポイントを整理し、介護事業者が押さえるべき要点をわかりやすく解説します。
■1|臨時改定として処遇改善加算が見直される背景
日本は急速な高齢化が進行し、介護現場の人手不足が深刻な社会課題となっています。介護職の離職率が高い原因のひとつは 賃金水準が他産業に比べて低いままであること。このため、厚生労働省は従来の3年ごとの介護報酬改定に先立ち、2026年6月に処遇改善を中心とした 臨時の介護報酬改定 を決定しました。
この改定の狙いは、介護職員の給与改善だけでなく、 介護従事者全体の処遇向上と長期的な人材確保 にあります。国は処遇改善加算の拡充により、現場のモチベーション向上や離職防止を実現し、介護事業全体の安定化を図ろうとしています。
■2|「処遇改善加算」の対象範囲が大幅に拡大
従来の処遇改善加算は主に介護職員を対象としていましたが、2026年6月からはその対象が 介護従事者全体に拡大 されます。ここで言う介護従事者とは、介護職だけでなく 介護支援専門員(ケアマネジャー)や訪問看護、訪問リハビリテーションのスタッフ を含む広い範囲を指します。
特に注目すべきは以下の新対象サービスです:
-
訪問看護
-
介護予防訪問看護
-
訪問リハビリテーション
-
居宅介護支援(ケアマネジャー業務)
これらは従来、処遇改善加算の対象外とされてきましたが、改定後は加算の対象となることで、 看護職・リハビリ職・ケアマネジャーの賃金改善が可能となる 点が大きなポイントです。
■3|加算率の引き上げと上位区分の新設
処遇改善加算の体系自体も大きく変わります。従来の加算区分Ⅰ・Ⅱに加えて、 生産性向上や協働化等の取り組みを要件とする「上位区分(例:Ⅰロ・Ⅱロ)」 が新設されます。これにより、同じサービス種別でも 取り組み内容に応じて加算率が大きく変動 するようになります。
例えば、訪問介護や通所介護では ICTを活用した 生産性向上への取り組み を行う事業所に対して、従来より高い加算率を付与することが可能になります。これは単なる賃金原資の確保だけでなく、 効率化・質向上を同時に促すインセンティブ設計 でもあります。
また、現行の加算率そのものも引き上げられるため、介護職員にとっては 月額約1万円〜最大1.9万円程度の処遇改善が見込まれる とされており、賃金ベースアップの直接的な効果が期待されています。
■4|事業所運営への影響と留意点
この制度改定は介護事業者にとって歓迎すべき賃金改善策ですが、一方で 対応すべき実務プロセスや要件が複雑化する という面もあります。
✅ 主な留意点
-
新しい区分の取得要件整理
上位区分を取得するためには、生産性向上の具体的な取り組みや協働体制の構築など、事業所ごとの実行計画が必要です。 -
加算対象外だった職種の給与配分ルール
従来の賃上げ原資の配分ルールは介護職中心でしたが、対象拡大に伴い 看護師・リハ職・ケアマネにも賃上げ原資を配分するルールを整備する必要 があります。 -
現場負担の可能性
審議会の段階では、委員から「制度が複雑すぎて小規模事業所が対応困難」という意見も出ており、 事務負担増への懸念 も指摘されています。
■5|処遇改善加算拡充がもたらす効果
この改定が実現すると、日本の介護現場に以下のような ポジティブな影響 が期待できます。
📌 賃金水準の底上げ
従来より高い加算率と対象範囲の拡大により、介護従事者全体の給与改善が進む可能性があります。特に多職種連携が求められる在宅サービスでは、 専門職の定着促進 につながるでしょう。
📌 人材確保力の強化
介護職は深刻な人材不足に直面していますが、待遇改善が進むことで 人材の応募・定着率向上 が期待されます。加えて、上位区分要件を満たす事業所は採用競争力の向上につながります。
📌 サービス品質の向上
生産性向上やICT活用へのインセンティブが設計されたことで、 業務効率の改善と質向上 の両立が促されます。
■まとめ:事業者が今すぐ取り組むべきこと
2026年6月からの処遇改善加算の改定は、介護現場にとって 賃金改善と人材確保の大きなチャンス です。しかし、その恩恵を最大化するためには、事業所独自の取組計画を策定し、 新たな加算区分への対応を戦略的に進めることが不可欠 です。
具体的には以下の点を検討しましょう:
-
生産性向上やICT導入計画の策定
-
多職種の賃金配分ルール整理
-
上位区分の要件を満たす職場環境整備
この制度改定を正しく理解し活用することで、介護事業者は 持続可能な運営と現場職員の満足度向上 を同時に実現できます。
年度の補正予算による補助金について、運用ルールの細部を明らかにするQ&Aを公表
厚生労働省は21日、介護職員の賃上げに向けて支給する今年度の補正予算による補助金について、運用ルールの細部を明らかにするQ&Aを公表した。
介護保険最新情報のVol.1462で現場の関係者に広く周知した。
今回のQ&A(第1版)は全23問。申請のスケジュールや賃上げの実施期限、対象経費の範囲、要件確認に必要な根拠資料など、補助金の活用に向けた実務的な規定が解説されている。
厚労省はこの中で、賃上げの実施時期に言及した。
今年3月末までに補助金の支給を受けた場合、昨年12月から今年3月末までの間に行うよう要請。今年4月以降に補助金の支給を受けた場合は、昨年12月から各自治体の実績報告書の提出期限までに行うこととした。
そのうえで、全国の事業所・施設に「可能な限り速やかに実施していただきたい」と呼びかけた。
また、賃上げに伴って増加する法定福利費の事業主負担分について、賃金改善に含めてよいという解釈も示した。
今回の補正予算による補助金は、介護職員1人あたり最大で月額1.9万円を支給するもの。ベースは月額1万円で、要件を満たせばプラス5千円、追加でさらに4千円と上乗せされる設計となっている。上乗せ部分については、「ケアプランデータ連携システム」への加入や「生産性向上推進体制加算」の取得などが要件として定められている。
厚労省は今回のQ&Aで、こうした要件を満たしていることを証明する根拠資料も紹介。以下のように例示した。
◯「ケアプランデータ連携システム」については、使用画面のスクリーンショット(撮影時点がわかるもの)
◯「生産性向上推進体制加算」については、体制届出
これらは一律の提出までは求められないが、事業所で2年間の保存が必要。都道府県から求められた場合は、速やかに提出しなければならないとされた。
厚生労働省は16日、来年度の臨時の介護報酬改定に向けた検討を重ねてきた審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)を開き、6月から実施する「処遇改善加算」の拡充の内容を明らかにした。
幅広い介護従事者に月額1万円の賃上げを届けるべく、既存の「加算Ⅰ」から「加算Ⅳ」の全ての区分で加算率を引き上げる。
あわせて、介護現場の生産性向上や協働化に取り組む事業所を評価するため、上位の「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」にそれぞれ新たな区分を創設。月額7000円分の上乗せ措置を講じる。これに定期昇給で見込まれる2000円をあわせ、月額で最大1万9000円の賃上げにつなげる考えだ。
新設される区分は、「加算Ⅰロ」と「加算Ⅱロ」。最上位となる「加算Ⅰロ」の加算率は、訪問介護が28.7%、通所介護が12.0%、特養は17.6%、老健は9.7%とされた。主なサービスの上位区分の加算率は以下の通りだ。

新設される上位区分(Ⅰロ・Ⅱロ)の取得要件には、介護現場の生産性向上や協働化の取り組みが位置づけられた。
厚労省は訪問系・通所系のサービスについて、「ケアプランデータ連携システム」への加入を取得要件に設定。施設系のサービスでは、既存の「生産性向上推進体制加算」の取得を求めるとした。介護現場の事務負担に配慮し、来年度中は事後の対応を約束する「誓約」があれば取得できる特例も設ける。
今後、厚労省は6月の施行に向けて関連通知やQ&Aなどを発出していく予定。
本記事では、介護事業所におけるキャリアパス要件について、
-
等級制度
-
評価制度
-
給与制度
の3つに分けて、介護専門社労士の視点から実務・事例・制度設計の考え方まで踏み込んで解説します。処遇改善加算への対応だけでなく、人材定着・育成・採用力向上を本気で考える経営者・管理者の方に向けた実践的な内容です。
【第1部】等級制度におけるキャリアパス要件の重要性
結論
等級制度は、介護職員が将来像を描き、安心して働き続けるための設計図です。キャリアパス要件を満たすためだけに形式的に作るのではなく、「人を育て、定着させる仕組み」として整備することが極めて重要です。
解説
介護事業所におけるキャリアパス要件では、「職位・職責・能力に応じた段階的な区分」が求められています。これを制度として具体化するのが等級制度です。
多くの介護事業所では、
-
新人
-
ベテラン
-
リーダー
といった暗黙の序列は存在しますが、それが制度として明文化されていないケースが大半です。その結果、職員からは次のような声が上がります。
-
「何年働けば評価されるのか分からない」
-
「資格を取っても待遇が変わらない」
-
「将来、管理職になれるのか見えない」
等級制度では、これらの不安を解消するために、
-
等級ごとの役割
-
求められる能力・スキル
-
到達基準(経験年数・資格・行動)
を明確にします。
等級制度の具体例
【介護事業所の等級モデル】
-
1等級:新人・補助業務(初任者研修)
-
2等級:自立した介護業務(実務者研修)
-
3等級:チームの中核・後輩指導(介護福祉士)
-
4等級:リーダー・主任
-
5等級:管理者・サービス提供責任者
このように段階を示すことで、職員は「次に何を目指せばよいか」を理解できます。
特に重要なのは、資格と役割を結び付けることです。介護業界では資格取得が努力の成果として分かりやすいため、等級制度と相性が非常に良いのです。
等級制度がない場合のリスク
等級制度がない事業所では、
-
昇格基準が管理者の主観
-
ベテランが評価されない
-
若手が将来を描けず離職
といった問題が起こりやすくなります。これは処遇改善加算の算定リスクだけでなく、慢性的な人材不足につながります。
Q&A
Q1:小規模事業所でも等級制度は必要ですか?
A:はい。人数が少ないほど、役割と期待値を明確にしないと不満が顕在化しやすくなります。
Q2:等級が固定化してしまいませんか?
A:定期的な見直しと評価制度との連動で、柔軟な運用が可能です。
【第2部】評価制度におけるキャリアパス要件の重要性
結論
評価制度は、キャリアパスを「実感できる仕組み」に変える要です。等級制度が地図なら、評価制度は現在地を示すコンパスと言えます。
解説
キャリアパス要件では、「能力・業績に応じた評価」を行うことが求められています。しかし介護業界では、評価制度が形骸化している事業所も少なくありません。
介護職の評価が難しい理由は、
-
売上や数字で測りにくい
-
チームプレーが中心
-
利用者満足度が見えにくい
といった点にあります。
そのため、評価制度では行動評価を中心に設計することが重要です。
評価項目の具体例
【介護職の評価項目例】
-
利用者・家族への対応
-
法令・ルール遵守
-
記録の正確性
-
チームへの貢献
-
後輩育成・指導
これらを点数化・ランク化し、等級ごとに求める水準を変えることで、キャリアパスと評価が連動します。
評価制度が整備されると、
-
職員が評価基準を理解する
-
面談が建設的になる
-
不満や誤解が減る
といった効果が生まれます。
評価制度がない場合の問題
評価制度が曖昧な職場では、
-
「頑張っても報われない」
-
「評価は上司の好き嫌い」
という不信感が蓄積します。これは離職理由として非常に多いパターンです。
Q&A
Q1:評価が甘くなってしまいませんか?
A:評価基準を具体化し、複数項目で判断することで主観を抑えられます。
Q2:評価者の負担が心配です
A:シンプルな評価シートから始め、運用しながら改善することが現実的です。
筆者の実体験
ある特養では、評価制度が形式だけの状態でした。評価項目を現場向けに再設計し、年2回の面談を実施したところ、「初めて評価に納得できた」という声が多く上がりました。
【第3部】給与制度におけるキャリアパス要件の重要性
結論
給与制度は、キャリアパスの最終的な出口です。等級・評価があっても、給与に反映されなければ制度は機能しません。
解説
キャリアパス要件では、「昇給・処遇改善の仕組み」が明確であることが求められます。ここで重要なのは、
-
等級制度
-
評価制度
-
給与制度
を必ず連動させることです。
給与制度では、
-
等級別の基本給レンジ
-
評価結果による昇給幅
-
資格手当・役職手当
を整理します。
給与制度モデル
【等級×評価×給与の連動イメージ】
-
等級3+評価B → 年○円昇給
-
等級3+評価A → 年○円昇給
このように仕組みを見える化することで、職員は将来の収入をイメージできます。
給与制度が不透明な事業所では、
-
昇給理由が不明
-
将来不安が大きい
という状態になり、採用でも不利になります。
処遇改善加算との関係
処遇改善加算は、キャリアパス要件を満たすことで安定的に取得できます。給与制度と連動させることで、
-
加算原資の使途が明確
-
職員への説明が容易
といったメリットがあります。
Q&A
Q1:原資が限られていても導入できますか?
A:はい。昇給幅を小さく設定し、段階的に改善する方法があります。また「原資ありき」でそれに合わせた分配方法の仕組みをつくることが可能です。
Q2:一気に給与を上げないと不満が出ませんか?
A:将来の見通しを示すことで、納得感は大きく向上します。
筆者の実体験
給与制度を等級・評価と連動させた介護事業所では、「なぜこの給与なのか」が説明できるようになりました。その結果、職員の不満が減り、定着率が大幅に改善しました。
まとめ
キャリアパス要件は、単なる処遇改善加算の条件ではありません。等級制度・評価制度・給与制度を一体で設計することで、人材定着・育成・採用力強化を同時に実現できます。
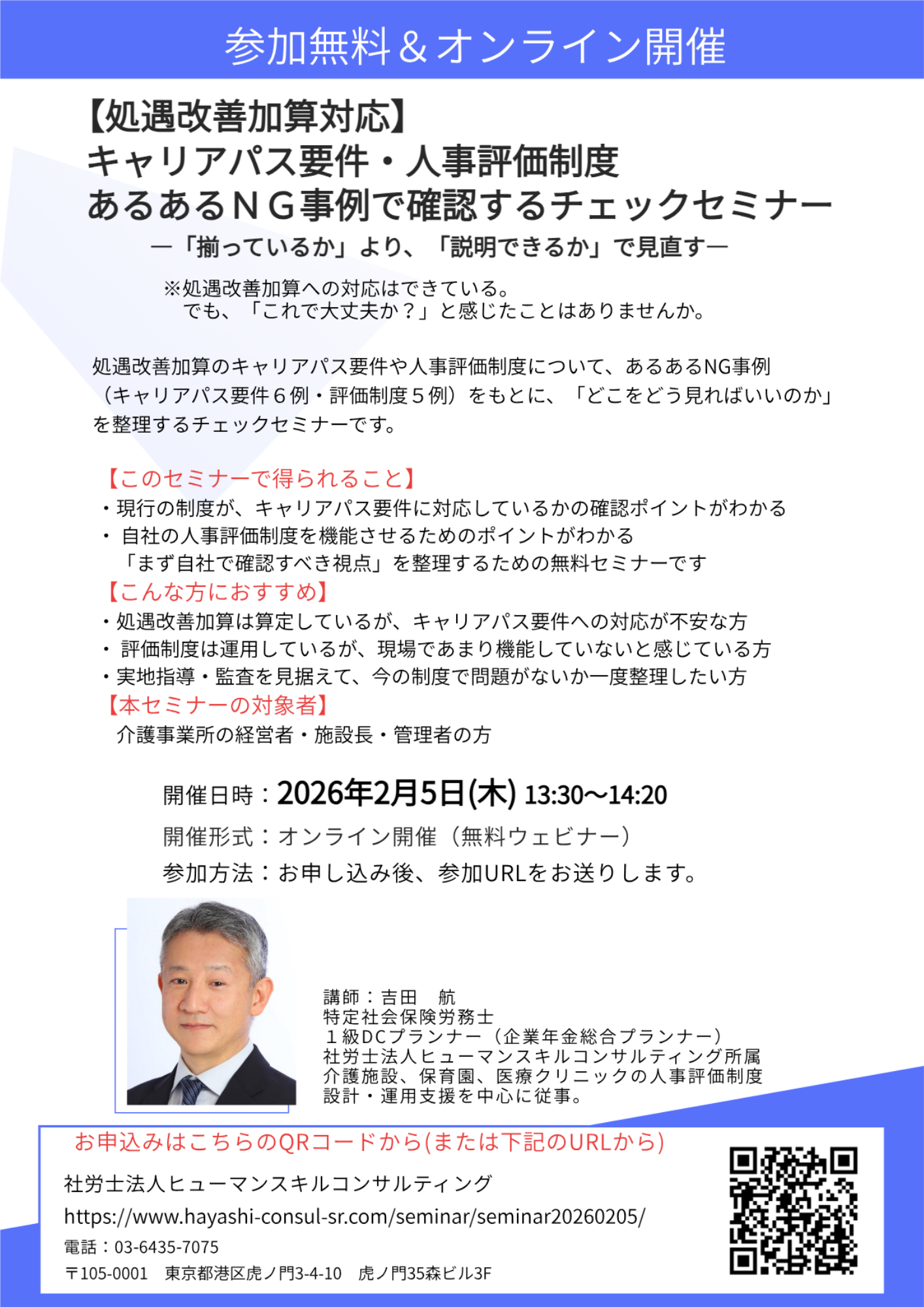
厚生労働省は14日に介護保険最新情報Vol.1461を発出した。インフレ対応や災害対策として介護現場に支給する今年度の補正予算による補助金について、交付要綱・実施要綱を周知した。
介護施設向けには、給食コスト・食材料費の高騰を考慮した支援に加えて、災害発生を想定した設備・備品の購入などに対する補助が用意された。
補助額は定員1人あたり合計で2万4000円となる。厚労省は支給要件や申請手続きなどの相談を受け付ける専用の電話窓口も開設した。
今回の要綱によると、物価高の中でも栄養バランスの取れた食事の提供を維持するための支援として、定員1人あたり1万8000円の補助金が支給される。
対象は特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ショートステイなど。補助金の使途は主に食材料費となる。
あわせて、災害時のサービス継続、避難対応に向けた設備・備品の購入費なども補助される。介護施設の場合、こちらの補助額は定員1人あたり6000円と定められた。
補助対象の例としては、衛生用品や医療用品、飲料水・食料品、ポータブル発電機、冷暖房機、簡易トイレなどがあげられている。このほか、夏の猛暑対策や利用者・職員の環境改善につながる設備・備品なども対象に含まれる。
この補助金の実施主体は都道府県。原則として、法人本部などが複数施設をまとめて対応する一括申請も可能だ。
実際の申請受け付け期間や提出様式といった手続きの詳細は、各都道府県から示される案内を確認する必要がある。厚労省は施策の早期実施を働きかけており、事業者は各自治体の情報を注視しておく必要がありそうだ。





